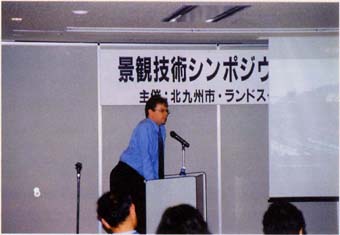基調報告「北九州市における新世紀の景観づくり」
デワンカー・バート(早大理工総研講師)
北九州一帯は、玄界灘と瀬戸内海に面した自然豊かな地で、かつては漁業や農業を主とした自給自足の生活を営んでいた。1901年、八幡製鉄所が操業を開始以後、百年間にわたって北九州は世界の鉄鋼産業をリードし、日本の重要な産業拠点として繁栄してきた。その絶えざる成長の時代で、どんどん北九州市へ人が集まり、産業も集積した。洞海湾の八幡製鉄工場は埋め立てによる日本で最初の工業団地となる。これは内陸の空地不足のため、洞海湾の埋め立てによって工業地域を拡大してきたためである。また、後背地は山に囲まれた地域であり、海岸と山の間の土地は住宅地として利用され、発展してきた。
それにより、北九州市の景観、特に、洞海湾周辺の地域が大きく変わったことで、人々の生活様式も変化してしまった。20世紀初頭ごろまでは、まちのどこからでも海岸へのアクセスが可能であったが、現在は洞海湾周辺を中心として、広範囲に工業用地が立地しているため、市民が海岸へアクセスすることはほとんど不可能になっている。
工業地帯の独特の景観及び工業地帯の再生が世界の工業都市の共通話題になっている。海外事例を取り上げながら、来る世紀の北九州工業地帯の景観を提案する。その一例としてドイツのルール工業地帯の新世紀景観の在り方及び再生プロジェクトについて紹介する。
・ 海外事例:エムシャー川流域の再開発プロジェクト計画
ルール工業地帯は埋蔵量の豊富な炭鉱地域として有名であり、19世紀以後、鉄鉱石や石炭の採掘に依存し、製鉄工業が発展してきた。続いて、機械、化学等の工業も発展し、さらに戦後は、電機機械工業、エレクトロニクスを中心とする先端技術工業が急速に発展した。産業開発によって、急速に産業関連施設、インフラ等が整備された。さらに、労働者集約のために田園都市型住宅街も作られ、ルール工業地帯の中心部に流れるエムシャー川流域は連鎖型の大規模市街地を形成するようになった。全流域の多くの河川が直線化されただけではなく、堤防を築く等河川の整備が行われた結果、周辺地域の排水が全てエムシャー川に流れ込み、水質汚染、土壌の汚染及び緑の破壊等、様々な環境問題が起き、エムシャー川の自然生態環境が壊滅された。
そこで、1989年にドイツ連邦政府及びノルトライン・ヴェストファーレン州政府を主催として、IBAエムシャー・ランドスケープ・パークのもとに、エムシャー工業地帯の再開発プロジェクト計画を発表し、再自然化工事が開始された。これは自然の姿を取り戻すための計画だけではなく、エムシャー工業地帯の自然環境の回復、さらには産業維持と新たな経済発展、産業のリストラクチュアリングを目指すものである。
都市の景観とは、見た目の景色だけではなく、その都市の歴史、文化、市民の日常生活、そのまちのよさ、記憶などを現わす。20世紀末、100万人都市として北九州市は成熟期を迎えていて、市街地の拡大は限界になっているが、北九州市にはより魅力のある都市の景観を創るための素材として「海・山・洞海湾岸の多くの緑地・産業史上の歴史的な工場建築などの産業遺産」が豊富に揃っている。これら現在ある、独特な素材を活かした景観づくりが必要なのである。今、世界の工業都市では、工業地帯独特の景観の再評価とその再生が共通話題になっている。北九州市には非常に多くの産業遺産が、海岸を中心にまち中に点在しており、この特徴のある風景と景観を再評価し、守っていく意識が重要である。
また、ここは山と海をはじめ、豊富で美しい自然に囲まれているにもかかわらず、残念ながら日常生活の中では、その美しい自然はあまりにも遠く感じられる。このため、既存の緑と水をネットワーク化して、洞海湾ウォーターフロント開発など、各所に自然拠点を回復して、ランドスケープベースで広域的に回復していく必要がある。現在、北九州市は「鉄都」から「エコ・テクノロジー都市」への転換を目指し、環境産業を柱とした「環境調和型都市」として蘇生しつつある。21世紀に向けて、20世紀になくしてしまった自然環境を回復し、水と緑に育まれ、自然と調和した生活様式を取り戻すための「環境調和型都市」の実現に当たって、新たに環境に配慮した景観づくりが課題となっている。
そこで、洞海湾を中心とする工業地域において、豊富な土地の中に緑や水のインフラを創造し、自然を甦らせ、海岸線の整備をすることによって、海岸へのアクセスを容易にし、魅力ある自然景観をつくる提案をしたい。こうした海岸緑地は、市民にとっても憩いやアメニティの場となる。海岸沿いの立地を生かし景観を創り出すことは、市民や観光客にとって、市全体が魅力的で長く住み続けたくなる都市になるのである。
使い捨ての時代は終わった。まち中の緑地、及び産業遺産を維持保存することによって、地域の歴史を後世に伝えることができる。また既存の建物を再利用することは地域の構造改革に寄与する。こうしたことは景観づくりにとって文化的にも重要な要素なのである。
来る21世紀、産業構造の転換によりIT産業や環境産業が台頭し、今後も第二次産業は衰退の一途をたどらざるを得ない。新世紀の景観づくりは、産業遺産を保存し、自然を取り戻すだけではなく、北九州工業地帯の自然環境の回復、さらには産業維持と新たな経済発展、産業のリストラクチュアリングを目指すものになる。特に、国際競争力のある環境産業および情報産業の関連企業等を誘致している北九州市にとって不可欠な政策のひとつになると思われる。中でも洞海湾岸及び海岸沿いは、新産業拠点として新しいものを取り入れながら、今ある「ポテンシャル」を生かした独自の景観づくりを進めることが重要である。
そこで、具体的には、新しいハードの整備促進、道路や鉄道等従来のインフラだけではなく、緑や水のインフラへの投資といった、実際に景観づくりを進めることも勿論であるが、その活動をホームページ等を利用し、広く国内外にvirtual景観としてアピールすることも、これからの時代は重要になってくる。こうした試みは、市民の景観に対する意識を高めるばかりでなく、観光目的の一つとしてまちの活性化を高める期待もできるだろう。
|