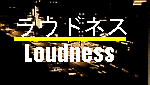
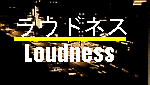
概要
ラウドネスとラウドネスレベルの関係
ラウドネスの歴史
Fletcherは純音の等ラウドネス曲線を、強さのレベルおよび感覚レベルの関数として示している。
ラウドネスレベルの表し方については、各国が独自の案で行う期間があったが、1936年にアメリカの騒音測定暫定基準は、ラウドネスレベルを次のように定めた。
ラウドネスの基準
| [1] | 任意の音ラウドネスレベルは、受信者の耳の位置で、その音と同じ大きさに聞こえる基準音の強さのレベルで表す。 |
| [2] | 基準音は1000Hzの平面進行波で、強さの基準は10 -16W/cm2とする。 |
| [3] | 基準音の大きさを測るとき、受信者は音源に向かって両耳を結ぶ線が音源から1mの位置とする。 |
その翌年、パリにおける国際会議で次の案が採択されている。
| [1] | ラウドネスレベルには phon、強さのレベルにはdBを採用する。phonもdBも従来のdBの定義に従う。 |
| [2] | 基準音は1000Hzの正弦平面進行波とし、基準点は10-16W/cm2の強さ、または 2×10-4dyne/cm2とする。 |
ラウドネスの進化
この曲線は、各種の純音について1,000Hz の純音と等しい大きさのレベルとなる点を結べば、下図のとおりとなり、多数の人による測定の平均値で,1961年にISO/R226に採用され、一般に用いられている。
ラウドネス曲線
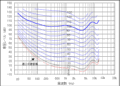
これらの曲線群の特色はレベルが大きいほど周波数特性は平坦であるが,小さいレベルでは、低音部が上がりこのあたりで耳の感覚が鈍くなっており、一方、4000Hzあたりの感覚がもっとも鋭いことなどである。
これと並行して指示計器による騒音のラウドネスレベルの概算値を求めたいという要求に基づいて,騒音計の聴感補正回路の研究が進められた。
UP DATE 3/13/1997
yano@gpo.kumamoto-u.ac.jp
Faculty of Architecture,Departmant of Engineering,Kumamoto University.
Copyright (c) 1996 S.Nagatomo in Yano Laboratory.