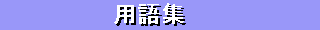
| 単語別 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |
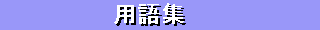
| 単語別 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |
- アノイアンス
- 音にかかわる不快感の総称。騒音に対する不快感は、物理的要因(音そのもの)だけではなく、 音に対する各種の要因によって規定される。その要因とは、
- ①騒音の発生状況に関する要因
- 例えば、夜間の騒音と昼間の騒音は、夜間の方が不快に感じる。瞬間の音と長時間継続の音は、 長時間の方が不快など。
- ②騒音の内容に関する要因
- 例えば、経験のない新奇な音など。
- ③聞く人の状態に関する要因
- 例えば、就寝前や起床したときは、聞き慣れた騒音も不快となり、他人の好きな音楽は、好きに慣れないなど。
- ④聞く人と音源に関する要因
- 例えば、音源が見えていると、見えていないときより不快に感じ、止められない音など。
単一の評価尺度ですべての騒音を評価できないのは、音に関してこのような要因が複雑に 絡み合っているためである。そのため数々の 騒音評価法が存在する。
- 暗騒音(あんそうおん)
- ある音を対象として考える場合、その音がないときのその場所における騒音を、対象の音に対して 暗騒音という。
- ISO(国際標準化機構)
- 国際間の交流と協力を増進するため、科学・技術・経済の分野において国際的標準化を 図ることを目的とする機関。本部はジュネーブにある。ISO規格(ISO/IS)と推薦規格 (ISO/IR)がある。
- 大きさのレベル(おおきさのれべる)
- ある音について、正常な聴覚を持つ人が、その音と同じ大きさに聞こえると判断した1000Hz 純音の音圧レベルの数値。単位記号は、phon。
- オクターブ
- 1.周波数2の音程。
- 2.1オクターブの音程を持った二つの音の間に含まれるいろいろな音程の音をひとまとめにしていう。
- 音の大きさ(おとのおおきさ)
- 音の強さに関する聴覚上の属性であって、小から大に至る尺度に配列できる。
音の大きさは、主として音圧に依存するが、周波数や波形などにも関係がある。
- 音の高さ(おとのたかさ)
- 聴覚上の音の性質の一つで、高低で表現する。
- 1.音の高さは主として音の周波数に依存するが、音圧や波形などにも関係する。
- 2.ある音の高さは正常な聴覚の人が聞いて、それと同じ高さを持つと思われる特定の音圧の 純音の周波数で表す事がある。
- 音の強さ(おとのつよさ)
- 音場中の1点において、音の進行方向に垂直な単位面積を、単位時間に通過する音のエネルギー。
- 音圧レベル(おんあつれべる)
- ある音の音圧と基準音圧との比の常用対数の20倍。基準音圧(0dB)は空気中の音の場合、 0.0002μbar{0.002Pa}(実効値)とする。この値は、平面進行波においては 10-16W/cm2にほぼ対応する。
- 可聴周波数(かちょうしゅうはすう)
- 正常な聴力を持つ人が聞くことができる周波数。だいたい15Hzから20000Hzまでの 周波数。
- 可聴範囲(かちょうはんい)
- 周波数の関数として表された最小可聴域の曲線と最大可聴域の曲線とで囲まれる範囲。
- 感覚レベル(かんかくれべる)
- ある音の音圧レベルとその音の最小可聴範囲とのレベル差。
- 環境基準(かんきょうきじゅん)
- 生活環境を保全するために望ましいとされる行政上の目標値である。
環境基準には特に強制力はない。公害対策基本法に基づいて,一般環境騒音と道路交通騒音、 航空機騒音、新幹線鉄道騒音に関わる環境基準がある。
- 結合音(けつごうおん)
- 二つ以上の純音を耳又は変換器に加えたとき、その非直線性によって生じた音。
- 減衰帯域(げんすいたいいき)
- フィルタなどにおいて、エネルギーの通過が阻止される周波数範囲。
- 最小可聴域(さいしょうかちょういき)
- 音の感覚を生じさせ得る最小音圧の実効値で、通常は音圧レベルによって表す。 最小可聴域は、音の性質、聞かせる手続き、音圧を測定した点などにも影響されるから、 必要な場合には測定条件を明記する。
- 最大可聴域(さいだいかちょういき)
- 音の感覚以外にほかの感覚、例えば痛感などを生じさせる最小音圧の実効値で、通常は音圧レベルで 表す。
- 雑音(ざつおん)
- 1.周期性がなく部分音に分解できない音。
- 2.主として電気通信回路において、望ましくない電気的騒乱。
- 指向性(しこうせい)
- 方向によって、レスポンスの変化があること。
- 指向性マイクロホン
- 音波の入射方向によって、感度が異なるマイクロホン。
- 実効帯域幅(じっこうたいいきはば)
- フィルタなどにおいて、次の二つの特性を持つ理想的フィルタの帯域幅。
- ①周波数に対して、一様なエネルギー分布の入力に対しては、実際のフィルタとエネルギーの 通過量が等しい。
- ②通過帯域内の純音のレスポンスは一定で、実際のフィルタの最大のレスポンスに等しく、 減衰帯域のレスポンスはない。
- 周波数分析(しゅうはすうぶんせき)
- 複雑な音又は振動について、その成分の大きさを周波数の関数として求めること。
- 純音(じゅんおん)
- 瞬時音圧が、時間の正弦関数である音。
- 振動計(しんどうけい)
- 振動体の変位、速度又は、加速度を測定する装置。
- ステレオ録音(すてれおろくおん)
- 立体音再生を目的として、一つの録音媒体に複数チャンネルの録音をすること。
- スペクトルレベル
- 連続スペクトルを持った音のある周波数を中心とした幅1サイクルの周波数帯域内に含まれる 成分音圧レベル。
- 接線法
- 騒音評価尺度の一つである。等しく評価されるバンドレベル相互間を曲線で結んだ評価曲線 図上に,対象騒音のバンドレベルをプロットし、その最大値によって評価する方法である。
- 騒音(そうおん)
- 望ましくない音。例えば、音声、音楽などの伝達を妨害したり、耳に苦痛、障害を与えたりする音。
- 騒音レベル(そうおんれべる)
- 騒音計で測定した聴感補正ずみの音圧レベル。
- ソン
- 音の大きさの単位。大きさのレベル40phonの音の大きさを1soneとし、正常の聴力を持つ人が 、1soneのn倍の大きさと判断される音の大きさをnsoneとする。
- 備考
- 1.近似的には、ソンで表される音の大きさSと音の大きさレベルPとの関係は、 log10S=0.03(P-40)である。
- 2. 上の関係が実験によって確認されている範囲は、20phonから120phonまでである。
- 帯域幅(たいいきはば)
- フィルタなどの通過帯域の幅。帯域フィルタの場合は、二つの切断周波数の差又は比(オクターブ) で表す。
- 帯域フィルタ(たいいきふぃるた)
- 周波数∫1から∫2までを通過帯域とし、0から∫1及び∫2から∞までを減衰帯域とするフィルタ。 この場合、∫1、∫2(>∫1)は、0及び∞を除く任意の値とする。
- 通過帯域(つうかたいいき)
- フィルタなどにおいて、エネルギーの通過が行われる周波数範囲。
- 強さのレベル(つよさのれべる)
- ある音の強さと基準音の強さとの比の常用対数の10倍。基準の音の強さは、空気中の音の場合、 10-16W/cm2=10-12W/m2とする。
- 定常波(ていじょうは)
- 同一周波数の進行波の干渉によって生じる空間的な振幅分布の定まった波。
- デシベル
- パワーや音の強さその他の量を比較するのに用いるディメンションのない単位。
- ①二つのパワーの量をW1、W2とすると、その差異は n=10log10W1/W2dB であるという。音の強さ及びエネルギー密度もこれに準ずる。
- ②音圧(粒子速度、電圧、電流)などパワーの平方根に比例する量は、二つの音圧をp1,p2 とするとその差異は n=20log10p1/p2dB であるという。ただしインピーダンスの異なる媒質中の量を比較する場合にも、このような表現を とることがあるが、この場合には①の定義による値とは、必ずしも一致しないから、条件を明記 する必要がある。
- ③基準値を約束して、パワー、音圧の強さ又は音圧などの絶対値を表すことにも使用される。
- 音色(ねいろ)
- 感覚上の音の性質の一つで、二音の音の大きさ及び高さがともに等しくてもその二音が異なった感じ を与えるとき、その相違に対応する性質。 音色は音のスペクトル、波形、音圧及びそれらの時間的変化などに関係がある。
- ノイジネス
- ノイジネスは航空機騒音の評価研究が進むに連れ明らかになり、K.D.Kryterらは、高音域成分の強いジェット機騒音の不快感がその他の日常に存在する騒音に比べて際立って大きい事実に着目し、音の大きさとノイジネスの相違を明らかにし、Perceived Noise Level(PNL)を提案した。 音の大きさに比べて、ノイジネスの概念には議論の余地が残っているが、音響心理実験による不快感の研究のためには重要な概念である。なお、Noisinessに対する日本語には、 「やかましさ」や、「うるささ」をあてることが多い。
- 白色雑音(はくしょくざつおん)
- 連続スペクトルをもつ雑音で、ある周波数範囲では、単位周波数帯域1Hzに含まれる成分の強さが 周波数に無関係に一定である音。電気回路において同様な性質を持つ波にも使用される。
- 倍音(ばいおん)
- 周期的複合音の各成分中、基本音以外のもの。第n倍音とは、基本音のn倍の振動数 をもつものをいう。
- バンドレベル
- ある周波数帯域内に含まれる音の音圧レベル。例えば、その周波数帯域の幅が1オクターブであるとき には、オクターブバンドレベルという。
- FFT
- 一般的に高速変換フーリエ方式による信号解析機のこと。FFT方式の周波数分析器は、 いろいろな周波数成分を含んだ入力信号を高速フーリエ変換することによって周波数ごとの成分に 分解してパワースペクトルを求めると同時に、振動騒音の問題を解決するのに役立つ各種の関数を 求める機能を持つ。
- フィルタ
- 特定の周波数帯域のエネルギーを通過させ、ほかのすべての周波数のエネルギーを阻止する変換器。
- 普通騒音計(ふつうそうおんけい)
- 騒音レベルの測定器。
- 複合音(ふくごうおん)
- 純音以外の音。
- Fletcher & Munson
- フルネームは、Fletcher.H & Manson。彼らは、1930年代に 純音のラウドネスを聴覚実験によって定量化する試みを行い、純音の等ラウドネス曲線を制作。 その曲線はその後長く国際的に使用された。しかし彼らは、純音のラウドネス研究にとどまり、 騒音の領域には進まなかった。
- 平面波(へいめんは)
- 波面が平面である波。
- 弁別域(べんべついき)
- 感覚で検知し得る刺激の最小変化量。
- マイクロホン
- 音響系から電気系へ変換する電気音響変換器。
- マスキング
- ①ある音に対する最小可聴域が、他の音の存在によって上昇する現象。
- ②ある音に対する最小可聴域が、他の音の存在によって上昇するときの上昇量をデシベルで表した もの。
- 無指向性マイクロホン(むしこうせいまいくろほん)
- 音波の入射方向に対して、感度がほとんど一様なマイクロホン。
- 明瞭度(めいりょうど)
- 試験用音声に含まれる音声単位の総数のうち、正しく聞きとれた音声単位の割合を百分率で 表したものであって、着目する音声単位(百分率算出に用いる音声単位)が単音又は無意味な 音節の場合に用いる。
- 明瞭度は、元来送話者、伝送系、受話者を含む全通話系の特性を表すものであり、もしも通話系の 一部の特性を表すために用いるときは、通話系の他の部分の特性を明示する必要がある。
- モノ録音(ものろくおん)
- 一つの録音媒体に、単一チャンネルの録音をすること。
- ラウドネス
- 耳がある音の刺激を受けたときに生ずる音の強さに関連した感覚の強弱の程度、 音の持つエネルギーに対する人間の感覚を、音の大きさ(ラウドネス)という。 音の大きさは主として音圧に依存するが、周波数や波形等にも関係がある。 周波数の異なる純音の大きさの相互関係については、 Fletcher & Munson の等ラウドネス曲線長い間値いられてきたが、現在はISOの 等ラウドネス曲線 が、国際的に使用されている。ラウドネスを取り扱いやすくしたものが、ラウドネスレベル (Loudness Level)である。
- ラウドネスレベル
- ある音について、正常な聴力を持つ人が、その音と同じ大きさに聞こえると判断した1,000Hz純音の音圧レベルの数値。 音の大きさそのものの感覚量については、音圧レベル40dBの1,000Hz純音の大きさを 1soneとする。