3.4.4 塀・つい立て・樹木による遮音
野外において音源と受音点の間に充分大きな塀を立てると、音源側はその反射によって音圧があがるが、受音側は影となって遮音効果が期待できる。この影の中の音圧レベルを求めるには、光の回折理論を用いて近似計算ができるが、それを実験的に修正したのが図3.12である。
これは最も基本的な条件として、自由空間に、ナイフエッジをもつ半無限に広がった障壁が、無指向性点音源と受音点の間に置かれている場合であって、減衰値とは、その障壁のない場合とある場合の差を表している。横軸は障壁がない場合とある場合の、伝搬経路の差δを半波長で割った数Nであり、実験曲線が一直線になるように調整してある。N=0でSOPが一直線になり、N<0はSPが見通せる範囲であるが、それでも5dB減衰することを示している。
現実に地上に立てた塀の場合は、地面その他の反射を考慮せねばならない。音源側における反射を含めて、塀の頂点Oにおける音圧を実測して基準値にすれば、実用上簡易で充分な近似が得られる。受音側では図3.13のように受音点Pの鏡像P’に対して同じ計算を行い、騒音に対しては位相を無視してエネルギー和をとればよい。
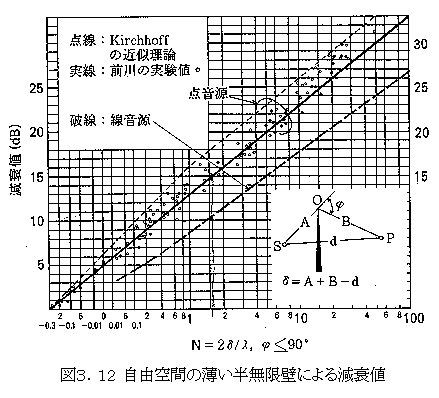
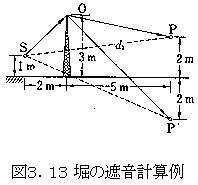
-
音源が無指向性でない場合は、塀の頂点で音圧レベルL0を実測し、P点の音圧レベルは
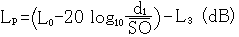 (3.38)
(3.38)
によって求まる。また道路のように線音源と考えられるときは
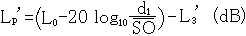 (3.39)
(3.39)
で近似する。ここでL3'は図3.12の破線を用いた計算値である。
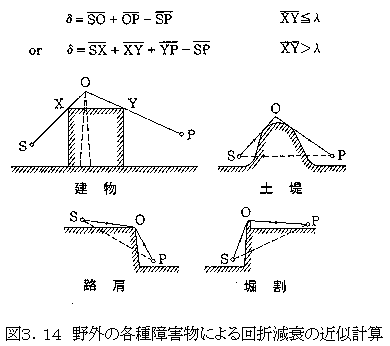
-
上記の方法によって塀による影の中のいかなる点の音圧レベルも、近似よく計算できるが、そのための条件として
1)塀の位置の音圧レベルの上下分布が、O点より上空で、しだいに減衰していること。
2)塀の長さが無限長とみなせること。受音点から見て両側に高さの数倍以上は延びている必要がある。
-
1)の条件を満足させるためには、塀の立てる前に、できるだけ高い位置まで上下分布を測定し、最高値となる位置よりも高くO点を定めることが望ましい。もし上空ほど音圧レベルが高くなるような特殊な場合では、塀による遮音効果はほとんど期待できない。また2)の条件が満足できない場合、すなわち、つい立ての場合は、上方のみでなく両側方からの回折を計算しなければならない。
厚さの大きい障害物の近似計算
塀の厚さが大きい場合や土堤、建物などの場合は図3.14のように経路差をとるとよい。
植樹や森林の遮音効果
植樹や森林などでは、吸音や散乱による減衰があるが、透過損失を得るには数10m以上の厚さと密度が必要で、生け垣のようなものでは回折もあり遮蔽効果は少ない。しかし、コンクリートの固い面に比べると吸音の効果もあり、視覚的な心理作用や、木の葉が風で発生する騒音によるマスキング効果も好まれるので、騒音対策に安全性を与える重要な手段と考えてよい。
 戻る
戻る
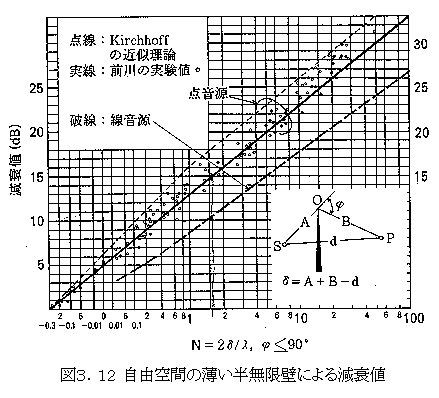
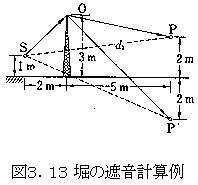
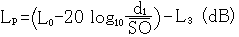 (3.38)
(3.38)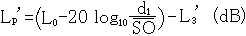 (3.39)
(3.39)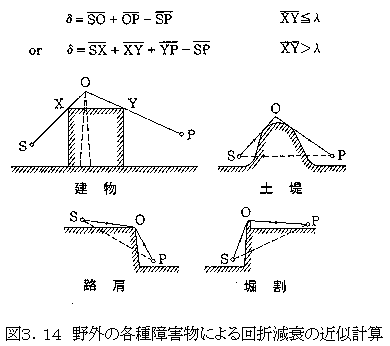
 戻る
戻る